マイホーム建築について
マイホーム建築のフロー
設計から工事竣工まで どんな事が行われるかご存知ですか?
1 構想・基本計画
- いろいろな条件
- ライフスタイル
- 予算の把握
2 建築士事務所と契約
- 信頼できる設計事務所
- 業務内容の説明
3 基本設計
- 立地調査(固有の条件地)
- 法令調査(建築基準法他)
- デザインの完成
4 実施設計
- 意匠(仕上げ・デザイン他)
- 構造(地盤・基礎・柱・梁)
- 設備(電気・給排水・空調)
5 施工会社/選定・契約
- 数社に見積もり依頼
- 見積書の内容を検討
- 相互信頼による契約
6 施工/工事監理
- 設計どおりに施工されているか
- 使用材料のチェック
- 色柄等の提案やアドバイス
7 完成/維持・管理
- 施工・設計事務所検査 → 手直検査
- 官庁又は確認検査期間による検査
- 機器類の取り扱い説明 使用した機材類の特性等の説明(お手入れ)
- 建物の劣化 → メンテナンスのアドバイス
建築士とは?
一級建築士・二級建築士・木造建築士
建築士とは、建物の設計、工事監理等を行う技術者で、建築士法に拠って定められた国家資格です。 資格には下記の種類があり、構造、規模、用途に応じて設計等ができる範囲が決められています。
| 構造 | 木造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、 コンクリートブロック造、無筋コンクリート造 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 高さ13mかつ 軒高9m以下 | 高さ13m又は 軒高9mを 超えるもの | 高さ13mかつ 軒高9m以下 | 高さ13m又は 軒高9mを 超えるもの | ||||
| 階数 | 段数1 | 段数2 | 段数3 | 階数2以下 | 階数3以下 | |||
| 無資格 | 100m2以下 | × | 30m2以下 | × | ||||
| 木造建築士 | 300m2以下 | × | 30m2以下 | × | ||||
| 2級建築士 | 制限無し | 100m2以下(特殊な場合は×) | × | 300m2以下 | × | |||
| 1級建築士 | 制限無し | |||||||
構造設計一級建築士による設計への関与が義務づけられる建築物
一級建築士の業務独占に係る建築物※1のうち、構造方法について大臣認定が義務づけられている
高さ60m超の建築物(建築基準法第20条第1号)及びルート2、ルート3、限界耐力計算による構造計算を行うことにより構造計算適合性判定(ピアチェック)が義務づけられている高さ60m以下の建築物(建築基準法第20条第2号)※2について、原則として、構造設計一級建築士による設計への関与が義務づけられます。
図書省略認定を受けた建築物や型式適合認定を受けた建築物は、対象とはなりません。
- 学校、病院、劇場、映画館、百貨店等の用途に供する建築物(延べ面積500m2超)
- 木材の建築物又は建築物の部分(高さ13m超又は軒高9m超)
- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物又は建築物の部分(延べ面積300m2超、高さ13m超又は軒高9m超)
- 延べ面積1,000m2超、かつ、階数が2以上の建築物
高さ60m以下の建築物でいかに該当するもの
- 木造の建築物(高さ13m超又は軒高9m超)
- 鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)
- 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)
- 鉄骨造の建築物(4階建て以上、高さ13m超又は軒高9m超)
- 組積造の建築物(4階建て以上)
- 補強コンクリートブロック造の建築物(4階建て以上)
- 柱間隔が一定上ある建築物や耐久壁が少ない建築物等これらの建築物に準ずるものとして国土交通大臣が指定したもの(平成19年国土交通省告示第593号に位置づけているもの)
増改築等の場合の考え方
増築、改築、大規模な修繕・大規模な模様替(以下「増改築等」という)の後に建築基準法第20条第1項又は 第2号に該当する建築物について、当該増改築等を行う部分が※1となる場合に、構造設計一級建築士による 設計への関与が必要となります。
設備設計一級建築士による設計への関与が義務づけられる建築物
階数が3以上、かつ、床面積5,000m2超の建築物について、設備設計一級建築士による設計への関与が義務づけられます。
増改築等の場合の考え方
増改築等を行う部分が、階数が3以上、かつ、床面積5,000m2超となる場合に、設備設計一級建築士による設計への関与が必要となります。
建築士事務所とは?
建築士事務所とは、建築士法に定められている、建築の設計整理業務を行う資格を持つ事務所のことです。 業務を行える建物の規模に応じて「一級、二級、木造」建築士事務所の3種類があり、各都道府県に登録 されています。 報酬の発生する設計・監理業務は、このような「建築士事務所」でないと、おこなうことが出来ません。
建築士事務所の役割
愛するものを守る家づくり 日々の幸せは安心して住める建物から
家を持ちたい、ビルを建てたいと願う気持ちは多くの人にとってロマンであり、大きな買い物です。
公的資金の調達も容易になり、マイホームにも手が届くとこまできているとお考えの方もいらっしゃることでしょう。
建築事務所は、家を建てる人(建築主)との信頼関係により建物の企画・設計を行い、工事を請け負う業者選定への助言や技術指導、設計・監理を行います。
又、家を建てるときは、色々な関連法規の制約を受け、その内容は複雑な要素をかかえています。 そのため段取りが悪かったり、打ち合わせが不十分な場合には、トラブルが起こりがちです。
そんな時に、専門知識を駆使し建築主の側に立って相談等に応じることも建築士事務所は大きな役割のひとつなのです。
仕事の内容
では、建物を立てるときに「設計・工事監理」がどのような位置づけにあるのか簡単にご紹介します。
1 建築相談
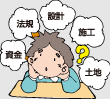 皆様方のご希望を遠慮なく話してください。建築資金、建築関係法規、手続きなどの相談から、設計・施工についての相談まで建築に関する全ての相談に応じます。
皆様方のご希望を遠慮なく話してください。建築資金、建築関係法規、手続きなどの相談から、設計・施工についての相談まで建築に関する全ての相談に応じます。
2 基本設計
 建物に対する考え方を伺い、敷地、立地条件などを調査し建築基準法関係法令に照らし合わせ、平面・立面などの基本設計図を作成し工事費の概算額も提示します。
建物に対する考え方を伺い、敷地、立地条件などを調査し建築基準法関係法令に照らし合わせ、平面・立面などの基本設計図を作成し工事費の概算額も提示します。
3実施設計
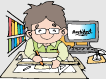 基本設計が出来上がり、貴方の建物に対する考え方も充分に理解し終えたところで、工事に着手します。意匠設計図、構造設計図、構造計算書、設備設計図、各工事仕様書、工事費積算書、建築関係諸手続きの書類が含まれます。
基本設計が出来上がり、貴方の建物に対する考え方も充分に理解し終えたところで、工事に着手します。意匠設計図、構造設計図、構造計算書、設備設計図、各工事仕様書、工事費積算書、建築関係諸手続きの書類が含まれます。
4 工事監理
 先ず、施行者(工事業者)の選定について助言を行います。工事期間中は、設計意図を施行者に明確に伝達し、各工事の施工検査を行い、工事が請負契約書などに示された諸条件に従って適切に施工されるよう監理を行います。
先ず、施行者(工事業者)の選定について助言を行います。工事期間中は、設計意図を施行者に明確に伝達し、各工事の施工検査を行い、工事が請負契約書などに示された諸条件に従って適切に施工されるよう監理を行います。
5 竣工
 建物の引越しに先立ち、建物内外の細部にわたって慎重に検査をいたします。
建物の引越しに先立ち、建物内外の細部にわたって慎重に検査をいたします。
6 アフターケア
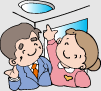 どんな優れた建物でも時には調子が悪くなることもあります。また、時代の経過とともに建物に要求される性能も変わってきます。そのようなときにはご相談くだされば適切な対応を行います。
どんな優れた建物でも時には調子が悪くなることもあります。また、時代の経過とともに建物に要求される性能も変わってきます。そのようなときにはご相談くだされば適切な対応を行います。
上記のような建物を建てるときに、「設計・工事監理」は大変重要な役割を果たしています。 しかし残念ながらその建築における大切な仕事はまだ一般の皆さまに充分に知らされてないのが現状です。 「設計・工事監理」の専門家集団である熊本県建築士事務所協会では、一連の震災を契機に広く一般社会に対し「設計・工事監理の重要性」を訴えかけています。
設計料の算定について

なお、業務報酬基準の対象外となる「設計に必要な情報を得るための調査、企画等の業務」等を実施する場合は、 別途、合理的な方法により算定し、加算する必要があります。
※詳しくは直接、建築士事務所にご相談ください。
戸建住宅の場合の標準業務量の算定について
令和6年国土交通省告示第8号による標準業務量の算定基礎を元に標準的な設計料を算定します。以下に例を示します。| ◉建築物(例)の概要 | |
|---|---|
| 敷地 | 整形・平坦な敷地 |
| 用途 | 戸建住宅(詳細設計を要するもの) |
| 延べ面積 | 150m2 |
| 構造種別 | 木造 |
| 階数 | 地上2階 |
| 構造 | 一般的な水準 |
| 設備 | 一般的な水準 |
| ◉標準業務量の算定(単位:人・時間) | ||
|---|---|---|
| 設計 | 工事監理等 | |
| 総合 | 290 | 120 |
| 構造 | 90 | 30 |
| 設備 | 75 | 32 |
| 小計 | 455 | 182 |
| 合計 | 637 | |
| (単位:人・時間) | |||||
| 床面積の合計 | 100m2 | 150m2 | 200m2 | 300m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (一)設計 | 総合 | 210 | 290 | 370 | 510 |
| 構造 | 71 | 90 | 100 | 130 | |
| 設備 | 57 | 75 | 92 | 120 | |
| (二)工事監理等 | 総合 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| 構造 | 25 | 30 | 34 | 42 | |
| 設備 | 24 | 32 | 39 | 51 | |
| (令和6年国土交通省告示第8号による) | |||||
設計についてのお問い合わせ
お問い合わせにつきましては熊本県建築士事務所協会まで電話にてお問い合わせください。 ☎ 096-371-2433
建築士事務所協会とは?
法律により定められた設計士事務所の団体です。
建築士事務所協会の法的な枠組として。「建築士法」第27条2には【建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会】が明記されています。
その法律に基づき、熊本県建築士事務所協会は、建築士事務所の業務の適正な運営や、建築主の利益の保護、公共の福祉の増進に寄与することなどを目的に密接なネットワークを構築しています。
また、熊本県建築士事務所協会は全国組織である(一社)日本建築士事務所協会連合会(日事連)に加盟しています。
建築の分野では建築士個人に求められる技術力は高度なものとなっています。又、その建築士の組織体である建築士事務所に改めて高いモラルと自己管理能力も強く求められています。
また、昨今のライフスタイルの変化、社会情勢の変化およびコンプライアンス重視型社会への対応などに即した建築設計及び工事監理の能力が求められており、その業務は年々複雑さを増しています。
熊本県建築士事務所協会は、そのような高度化する今日の建築界の動きや建築士事務所の経営及び業務に必要な情報の提供等、多様な事業を行って、「団体による自律的な監督体制の確立」を実現すべく組織された建築士事務所の団体です。
私たちはこんな活動をしています
 建築士事務所協会は、「建築士事務所憲章」の精神にのっとり、地域の皆様と様々な交流を促進しています。
建築士事務所協会は、「建築士事務所憲章」の精神にのっとり、地域の皆様と様々な交流を促進しています。その一つが建築無料相談です。皆さまの住まいづくりのお手伝いをしたり、設計や工事監理の段階で生じた問題や悩みごとの相談に応じます。
 建物の地震に対する耐久性がどれだけあるかを建物の現地調査することと建物の設計図の内容により耐震診断基準にて計算を行います。この計算までを全体で耐震診断と言います。
建物の地震に対する耐久性がどれだけあるかを建物の現地調査することと建物の設計図の内容により耐震診断基準にて計算を行います。この計算までを全体で耐震診断と言います。耐震診断を行うことで、耐久性の度合いを把握でき、安全に使用する為に補強が必要であるかの判断ができます。建築士事務所協会では、この耐震診断業務を実施しています。
 建築士事務所協会員は、新しい情報や技術を習得する為に、定期的に講習会や説明会等を開催し、技術の研鑽に努めております。
建築士事務所協会員は、新しい情報や技術を習得する為に、定期的に講習会や説明会等を開催し、技術の研鑽に努めております。又、建築基準法やその他の法律が改正された時点でも、その周知のために随時、講習会を開催しております。
耐震診断業務のご案内
平成28年4月に発生いたしました熊本地震以降、耐震診断につきましては多くのお問合せをいただいております。
耐震診断に関するご相談等につきましては個別に対応させていただいて おりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。
昭和56年5月31日以前に建築確認申請を受理された建物で、下記にあげる建物
・老朽化が進んでいる建物
・壁の少ない建物
・ピロティのある建物
・壁または窓の配置が偏っている建物
・多数の人が利用する建物 (病院・大規模店舗・大規模事務所等)
・階数が3以上の建物
経験豊かな当事務所協会員による診断により、 建物の安全性を確認されることをお勧め致します。
また、「耐震診断」により、補強が必要との判定がでた場合には 補強工事をお勧めします。
費用について
「耐震診断」の費用は、延べ面積や構造により異なります。
費用については当協会で概算をお見積り致しますので、事務局までご連絡ください。
TEL 096-371-2433 FAX 096-371-2450
耐震診断お役立ち情報
- 木造住宅耐震診断関係
- 一般財団法人 日本建築防災協会 - 木材住宅の耐震診断・改修
木造住宅の耐震診断Q&Aや、一般的な耐震診断費用が確認できます。 - マンション(共同住宅)耐震診断関係
- 一般財団法人 日本建築防災協会 - 建築物の耐震診断・改修
マンション(共同住宅)の耐震診断Q&Aや、一般的な耐震診断費用が確認できます。 - 誰でもできるわが家の耐震診断
- 一般財団法人 日本建築防災協会 - 誰でもできるわが家の耐震診断
リーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」はこちらから見ることができます。 - 無料相談(熊本住宅センター)
- 一般財団法人 熊本県建築住宅センター - 無料住宅相談
毎月2回開催しています。参加建築士は熊本県建築士事務所協会員です。
建築に関する各種相談
熊本県建築士事務所協会へのご相談
建物を建てるときは、色々な関連法規の制約を受け、その内容は煩雑な要素を抱えています。
建物の計画を進めていく過程では、さまざまなトラブルが生じることもしばしばあります。
そのような時に建築に関する専門知識を駆使し、建築主の立場で相談等に応じることも建築士事務所の大きな役割の一つです。
本協会では、地域の皆さまの建物や住まいづくりのお手伝いや、設計や工事の段階で生じたトラブルなどの相談を随時受付けております。
お気軽にご相談下さい。
熊本県建築住宅センターでの無料相談会
また、一般財団法人熊本県建築住宅センターにおいて、定期的に無料相談会を実施しており、建築(住宅)についての設計、施工、リフォームなどに関することについて相談を、一級建築士・弁護士・税理士といった、それぞれの専門分野のエキスパートによる無料住宅相談を行っております。
相談は事前の予約が必要ですので、事前にお問合せください。
建築士事務所がおこなった業務に関する苦情解決
本協会では、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法人として、同法第27条の5に基づく、苦情解決業務を行っております。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が、建築主等からの、熊本県内に事務所をおく建築士事務所がおこなった業務に関する苦情に対し、相談に応じ必要な助言し、事情の調査を行うとともに、当該建築士事務所の開設者に迅速な処理を要求するなどを実施して、苦情の解決をはかるものです。
苦情解決の申し出の方法
建築士事務所がおこなった業務に関して苦情を申し出される建築主及びその他の関係者の方は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただき、本協会から面接日時の通知いたします。
その時間においでいただきますと、専門の建築士が相談に応じます。
なお、係争中のものなど内容によっては対応できないものがあります。
下記の注意事項をよくご確認の上、お申込みいただきますようお願い致します。
苦情相談申込書(様式1)
注意事項(様式1別添)


㈱ビルド総合設計.jpg)
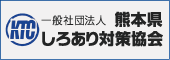
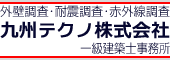
.jpg)


.jpg)

画像データ(バナー用)㈱平島0214.jpg)
